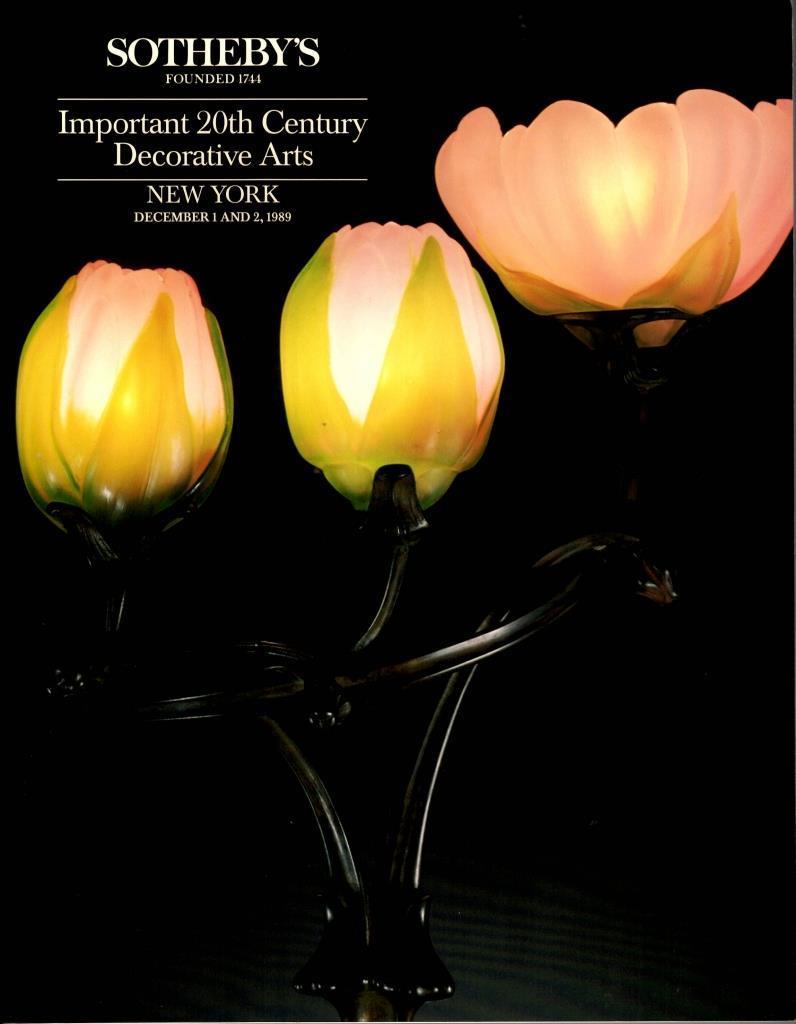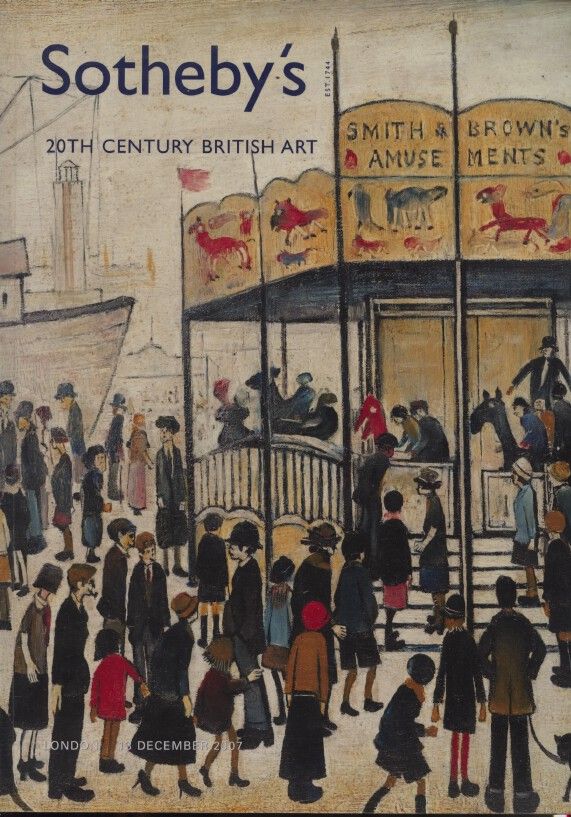下はジム・ジャームッシュ監督の2013年の映画、『オンリー・ラヴァーズ・レフト・アライヴ』の主人公アダムの部屋に飾られているポートレイトたち。
映画自体は吸血鬼モノであり、ラブストーリーということもあって未見だが、ミュージシャンであるアダムの部屋のシーンだけでも強烈な印象を残す。
これらはアダムの好きな人たちであり、ミュージシャンとしてのアダム、人間としてのアダム、そしておそらくは恋人としてのアダムに何らかの影響やインスピレーションを与えている人物たちなのだろうけれど、この部屋にもまた(当たり前のように)間接照明が用いられて、部屋に奥行きと静けさと落ち着きを与えている。
映画は観ていないが、アダムの部屋の写真を見たのは2~3年前。当時これらのポートレイトの何人の名前を知っているか試みた。
今は答えを知ってしまっているが、初見当時わかったのは
1、2、6、7、8、9、10、11、14、16、17、18、19、22、23、
26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、42、
43、44、49、51、52、53、55、56、57、
 |
 |
「本棚の中身を見ればその人がわかる」というけれど、こういうのを見ると、最早一目瞭然という感じがする。
このような部屋に強い関心を抱くと同時に、果たして自分が同じような部屋をつくり、敬愛する人物の肖像を60も並べることができるかと想像すると、どうもそれは難しいように思える。
わたしはただ作品を知っているだけで、彼や彼女の現実を知らない。たとえばわたしはショパンの音楽が好きだが、ショパンという人間がどのような人物であったかは、彼の身近にいた人達しか知り得ない。よく知りもしない人物を、その作品のみを以て愛することは、わたしにはできそうにない。
' Only Lovers Left Alive ' 「恋する者たちのみが生き残る」
アイドル(偶像、ヒーロー)が何十人いようと、生き残ることはできない。
何故なら彼・彼女らは、わたしだけのーわたしのためのヒーローではないのだから。
わたしを生かしてくれるのは、わたしと向かい合ってくれる誰か以外にはない。
それを恋と呼んでも、愛されることと言ってもいい。
アダムの部屋に飾られている数多くのヒーローたち。
けれども多くのアメリカ映画の登場人物たちは、家族の、子供の、また恋人の写真を、常に自分の傍(かたわら)に置いている。ベッドサイドに、オフィスのデスクの上に、また財布の中に、そして旅行に行く時にはトランクに詰めて・・・なぜならばそんな身近で名もない存在こそが、彼や彼女を愛し抱きしめてくれるかけがえのない本当のヒーローなのだから。
ポートレイトの人物の名前は こちら
(画像をクリックすると大きな画面で見ることができます)
あなたは何人わかりますか?
□追記□
上記リンクで、皆があれこれと名前を挙げているのがとても興味深い。
特に#18を「マックス・ベックマン?」と言っている人が居るが、確かにこの写真はマックス・ベックマンのセルフ・ポートレイトにそっくり!
 |
| マックス・ベックマン Self-Portrait with a Cigarette, Max Beckmann. Germany (1884 - 1950) |
 |
| ルイス・ブニュエル |